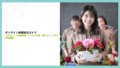「オンライン秘書って聞いたことはあるけど、実際どうなの?」
「初めてだから、何を頼めばいいのか全然わからない…」
「リモートでちゃんと伝わるのか心配だし、ミスがあったら困るかも」
──このような不安をお持ちの方、少なくないのではないでしょうか。
近年、リモートワークの普及や業務のデジタル化を背景に、「オンライン秘書」という新しい働き方・依頼スタイルが急速に注目を集めています。かつては大手企業の一部が導入していたような秘書業務を、今ではスタートアップ企業や中小企業、さらには個人事業主まで、多くの方が「ちょこっと」頼れる存在として活用しはじめています。
とはいえ、初めて「オンライン秘書」を検討する方にとっては、まだまだイメージしにくい存在かもしれません。
- どんな仕事をお願いできるのか
- 料金や契約の仕組みがどうなっているのか
- 対応してくれる人のスキルは信頼できるのか
- そもそも、外注するのってちょっとハードル高そう…
という「漠然とした不安」を抱えています。
さらに、社会全体として「人手不足」が深刻化している今、業務の一部をアウトソーシングしたいと考える経営者や管理者の方は増えています。
特に中小企業やベンチャー企業では、採用活動にコストや時間がかけられず、必要な時に必要なスキルを持った人材を確保するのが困難な状況です。さらに正社員として雇用する場合、固定費や教育コストが大きな負担になりがちです。
こうした背景のなかで注目されているのが、オンライン秘書という柔軟なリソースの確保手段です。
オンライン秘書は、地方・郊外・海外など、地理にとらわれずに全国から優秀な人材を集めることが可能です。実際、「元大手企業で働いていた方」「在宅で子育て中の元プロフェッショナル」「複数企業をサポートしているフリーランス」など、スキル・経験ともに非常に高い人材が多数登録しています。
つまり、従来なら雇用という形でつながるのが難しかった優秀な人材と、「必要なときに、必要な分だけ」つながれるのが、オンライン秘書の強みでもあります。
この記事は、そんな“オンライン秘書を初めて利用する方”に向けて、
- オンライン秘書の基本的な仕組みや特長
- 最初の依頼におすすめの業務例
- 不安を減らす依頼のコツと準備法
などを、やさしく・わかりやすく解説していきます。
これまで社内で抱えていた雑務、ずっと手を付けられなかった作業──
「外注」や「リモートでお願いするなんて無理」と思っていた方でも、
読み終わった頃には、「あれ?これなら私でもお願いできるかも」と思っていただけるように作成いたしました。
そして、なによりも大切なのは、最初から完璧に使いこなそうとしなくていい、ということ。
初めてのオンライン秘書なので、分からない、知らないは当たり前。
まずは一歩を踏み出すことが最大の成果です。
ちょっとだけ手放してみる。
ちょっとだけ相談してみる。
ちょっとだけ時間が空いて、ちょっとだけ仕事が整理できる。
その「ちょっと」の積み重ねが、やがて大きな安心感につながる──
そんな新しい働き方のパートナーとして、オンライン秘書の可能性をぜひ知っていただければと思います。
次章では、そもそも「オンライン秘書とは何か?」を、基礎から解説していきます。
オンライン秘書とは?
「オンライン秘書って、結局どういう仕事をしてくれるの?」
「社内にいる秘書さんと、何が違うの?」
初めてオンライン秘書という言葉を聞いた方にとっては、やや抽象的でつかみづらいかもしれません。ここでは、オンライン秘書の基本的な特徴や、一般的な秘書との違いを、できるだけシンプルに説明していきます。
そもそも「オンライン秘書」とは?
オンライン秘書とは、業務を“リモート”でサポートするパートナーのことです。
インターネット経由でつながり、日々の事務作業やアシスタント業務を遠隔で手伝ってくれます。
サポートする業務も秘書業務の枠を飛び越えて、リモートで対応出来る業務なら何でも依頼することが出来ます。
依頼者と直接会うことはありませんが、メールやチャット、Zoomなどを使って、業務を遂行します。
つまり──
🟢 オフィスにいないけど、チームの一員のように働く存在
🟢 雇用ではなく“業務委託”としてお願いできる外部の助っ人
これが「オンライン秘書」です。
オンライン秘書と社内雇用・派遣雇用との違い
| 比較項目 | オンライン秘書 | 社内雇用・派遣雇用 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 業務委託 (スポット・時間契約など) | 雇用契約 (正社員・派遣社員など) |
| 勤務場所 | リモートワーク | オフィス常駐 |
| 稼働時間 | 必要な時間だけ 曜日や時間の指定も可能 | フルタイム 固定のシフト制が一般的 |
| 導入スピード | 最短3日で稼働開始可能 | 面接・採用手続き が必要で数週間〜 |
| コスト感 | 月数万円から 社会保険や福利厚生不要 | 雇用コストがかかる (年収・保険・教育費など) |
このように、オンライン秘書は「必要なときに、必要なだけ」使える柔軟なサポート役として、多くの事業者から注目されています。
どんな人がオンライン秘書として働いているの?
実はオンライン秘書として活躍しているのは、非常に多様で優秀な人材です。
- 元・大手企業の事務職経験者
- 子育てや介護と両立しながら自宅で働きたい方
- フリーランスで複数社をサポートしているプロの秘書
- 士業資格やITスキルを持った専門人材 など
従来の雇用では出会えなかったような“高スキルな人材”に、地理を超えてつながることができるのがオンライン秘書の魅力です。
とくに初めてオンライン秘書を利用される方には、スキル面や信頼性が心配なこともあるかもしれませんが、多くのサービスでは秘書の選定・教育・マッチングをしっかり行っているため安心です。
オンライン秘書に依頼できる主な業務(ざっくり分類)
オンライン秘書が対応できる仕事は、事務作業を中心にとても幅広いです。
よく依頼される業務カテゴリ:
- スケジュール管理・日程調整
- メール対応・問い合わせの一次返信
- 資料作成・データ入力・集計
- 経費入力・請求書作成
- SNS投稿の下書きや予約設定
- 議事録作成・会議準備・事前調査 など
他にも
「それ、毎回自分でやってるけど、地味に時間取られてるんだよな…」
そんな業務こそ、オンライン秘書に任せることで効果を実感しやすい分野です。
難しいのは「使いこなすこと」ではなく、「最初に何をお願いするか決めること」
オンライン秘書は、自分の右腕になってくれる存在ですが、初めての場合は「まず何からお願いすればいいか分からない」と戸惑う方が多いです。
ですが問題ございません。
オンライン秘書は、依頼者が慣れていないことを前提に、しっかりヒアリングをしながら「依頼の仕方」そのものもサポートしてくれます。
初めての依頼はここから!おすすめスタート例
「何からお願いすればいいか分からない」
「いきなり難しい仕事を頼んで失敗したらどうしよう…」
オンライン秘書を初めて使う方にとって、最初の一歩はとても重要です。
どんなに優秀な秘書でも、依頼内容が曖昧だったり、ゴールが共有されていなかったりすると、思わぬすれ違いが生じてしまいます。
ですがご安心ください。オンライン秘書サービスは、最初の依頼に慣れていない方がほとんどという前提で、ていねいに対応してくれる体制が整っています。
この章では「初めての依頼」にぴったりな、シンプルかつ効果の実感しやすい業務を具体的にご紹介します。
スタートにおすすめの業務TOP5
① データ整理・リストの整形(Excel/スプレッドシート)
〇なぜおすすめ?
→ 名刺、注文履歴、顧客情報などの“ぐちゃぐちゃデータ”を、見やすく使いやすい形に整えてもらえる。
依頼例:
「このExcelの顧客名簿、重複を消して、会社名の表記を統一してください。部署と電話番号の列も追加してまとめ直してもらえますか?」
「この資料みたいな感じにしてもらえますか?」
ポイント:AIでは判断しきれない“人のルール感”が活きる作業。手間のかかる地道な業務だからこそ外注の効果が明確です。
特に新規事業を検討されている会社様に重宝されています。
② 資料の整形(パワポ・Word・Excel)
〇 なぜおすすめ?
→ 自分が作成した“たたき台”の資料を整えてもらうだけで、仕上がりが見違える。
依頼例:
「こちらのPowerPointを見やすく整えてください。グラフは青系で統一、文字サイズは14pt以上でお願いします」
ポイント:「どう整えると見やすいか?」のプロ視点も入り、自分では気づかなかった改善点に気づけます。
③ スケジュール調整・カレンダー登録・日程調整のやり取り
〇 なぜおすすめ?
→ 曜日や時間、候補日を伝えるだけで、日程調整とカレンダー登録まで任せられる。
日程調整のやり取りを丸投げする。
・ 依頼例:
「A社とのミーティング調整をお願いします。来週の火〜木で13時以降が候補です。Googleカレンダーに登録もお願いします」
<日程調整のやり取りを丸ごと依頼する方法。>
「ミーティングの調整ですが、この方(オンライン秘書)へ日程調整の連絡を入れてください。」
⇒後日カレンダーに反映された旨の報告を受け取る
ポイント:調整メールやチャットに割かれていた時間が大幅に削減され、即・効果を感じられます。
④ SNS投稿の予約設定
〇 なぜおすすめ?
→ すでに用意している画像や文面をツールに登録してもらうだけ。操作不要で投稿が完了。
ニュアンスやテーマだけを依頼し、画像と文面も丸ごと依頼も可能。(※プレミアムプラン対応)
・ 依頼例:
「今週のInstagram投稿画像3点を添付します。文面はフォルダのテキスト通りに、火・水・金の午前10時に予約投稿してください」
ポイント:投稿のタイミング忘れやバラつきを防げ、継続運用の下地が整います。
特にSNSのような継続が効果をに影響する業務にうってつけです。
⑤ Webリサーチ・情報の整理と要約
〇 なぜおすすめ?
→ 「必要な情報を集める」+「わかりやすくまとめる」は、地味だけど時間がかかる作業。
秘書の調査力が光る業務です。
また、それらを基にマニュアルやテンプレの作成もお手の物です。
・ 依頼例:
「来月の展示会で話題になりそうな業界トピックを調べて、5社分の最新情報を要約してください。各社1ページ程度に整理をお願いします」
ポイント:単なる検索では拾いきれない“比較”や“要約”を含むリサーチは、人による判断が活きる分野。初依頼でも依頼の成果が見えやすく、「お願いしてよかった!」を実感しやすい業務です。
単発依頼でもOK。「まずは1つ試す」スタイルが主流です
オンライン秘書サービスの多くは、月10時間~の時間契約や、1件単位でのスポット依頼にも対応しています。
- たとえば1回あたり2時間の業務を、週1〜2回だけ依頼するという使い方も可能です。
月10時間単位から契約できるので、無理なくスタートできます - 今月だけ頼みたい
- 特定の業務だけ外に出したい
──そんな柔軟なニーズに応えられるのが「雇用」ではなく「外部パートナー」の良さでもあります。
もちろん、秘書さんとの相性が合わなければ、変更相談ができるサービスも多く、不安なくスタートしやすい体制が整っています。
不安をなくすための準備とコツ
オンライン秘書に初めて依頼するとき、多くの方が感じるのは次のような不安です。
- 「どうやって依頼内容を伝えたらいいのか分からない」
- 「ちゃんと意図通りに仕上がるか心配」
- 「細かいことを一つ一つ説明するのって、逆に面倒じゃない…?」
初めての外注に不安を感じるのは当然です。だからこそ、「依頼の準備」と「伝え方」にちょっとしたコツを取り入れることで、ぐっとスムーズにスタートを切ることができます。
この章では、オンライン秘書をはじめて利用する方が押さえておきたい“事前準備”と“依頼のポイント”を、やさしく解説していきます。
1. 最初に決めるのは「目的」ではなく「困っていること」
「これをやってほしい!」というゴールを最初から明確に持っていなくても大丈夫です。
むしろ、「今ちょっと困っていること」「なんとなく面倒に感じていること」を言語化するだけでも十分。そこから一緒に“依頼に落とし込む”サポートをしてくれるのが、オンライン秘書の大きな価値です。
✅ 例:
- 「日程調整のメールが多すぎて管理できてない」
- 「請求書を作るのが面倒で、月末が毎回バタバタする」
- 「SNSを定期的に更新したいけど、手が回っていない」
👉「困っていること」を起点に、「だったらこの業務を任せてみましょうか」という形に進めるのが理想です。もちろんそれによって担当者の生産性やコア業務の進捗が改善されるのが最も理想的です。
🔸よくあるご相談:「事務・経理が辞めるので、代わりをお願いしたい」
実際にいただくご相談の中で多いのが、「担当していた事務や経理のスタッフが退職するので、そのままオンライン秘書に代わってほしい」というご要望です。
しかし、これは一見シンプルなようで、実は解決すべき課題が非常に多く、私たちとしては安易におすすめできないケースでもあります。
たとえば──
- 経理宛ての郵便物の処理(請求書・領収書など)
- 原本書類の収集・押印・保管
- 書類や伝票の物理的なやりとり
といった、“現場での物理対応”が前提となっている業務については、オンライン秘書単独で完結させるには無理があります。これらを外部でまかなうには別途予算が必要になり、「コストを抑えるためのオンライン秘書」という本来の目的から外れてしまうことも。
✔ オススメの解決策:「次期担当者が決まるまでの“代理経理”としての活用」
そこで、私たちがおすすめしているのが「次期経理担当が決まるまでの代理経理」として、オンライン秘書を一定期間利用する方法です。
具体的には──
- 前任者が退職するタイミングに合わせて、オンライン秘書が業務の引き継ぎを受ける
- 一時的に発生する郵便物の確認や書類回収は、社内のアルバイトや兼務スタッフが対応(コストをかけず、限定的に)
- 秘書が実務を遂行しながら業務内容を整理・マニュアル化
- 後任が採用されたら、そのマニュアルをもとに引き継ぎを実施
このような“つなぎ役”としてのオンライン秘書の活用は、非常に相性がよく、
- 採用を急がず、じっくり後任を探せる
- 業務の棚卸しが同時にできる
- 引き継ぎが形式化され、属人化を防げる
という、副次的な効果も得られます。
“代わりを探す”のではなく、“つなぎ役を担ってもらう”。
このような視点でオンライン秘書を活用することで、無理なく・無駄なく、業務の安定と再設計を進めることができます。
このように、最初から「完璧な目的」や「明確な依頼内容」がなくても問題ありません。
いま抱えている「困った」をそのまま伝えてみることで、新しい解決策が見えてくるかもしれません。
2. 依頼内容は「3点セット」で伝えると伝わりやすい
オンライン秘書への依頼は、「何を」「どうしたいか」「いつまでに」をセットで伝えると、驚くほど認識違いが減ります。
【依頼3点セットの型】
| 項目 | 例 |
|---|---|
| ① 何を | ○○の議事録をまとめてほしい |
| ② どうしたいか | 発言者ごとに要点を分けて、PDFでまとめてほしい |
| ③ いつまでに | 明日の17時までに納品してもらえると助かります |
🟢 これをチャットやメールでそのまま伝えるだけでもOKです。
もし余裕があれば、過去の類似資料・テンプレート・参考URLなどを添付すると、仕上がりのブレがかなり少なくなります。
3. ツールを決めて、やりとりの“見える化”を
やり取りの履歴が残らないと、依頼ミス・確認漏れが起こりがちです。
オンライン秘書との連携では、以下のようなツールを使って「タスクと進捗の見える化」をするのがおすすめです。
よく使われるツール例:
| 種類 | ツール名 | 用途例 |
|---|---|---|
| チャット | Slack / Chatwork / LINEなど | 日常的なやり取り、進捗報告など |
| タスク管理 | Trello / Notion / Google Tasks | 依頼内容の管理、進行中タスクの把握 |
| ファイル共有 | Google Drive / Dropbox | 資料や素材の共有、納品ファイルの受け取り |
ツールに慣れていない場合でも、オンライン秘書側がセットアップや使い方をサポートしてくれるので、遠慮せず相談してみてください。
4. 「完璧な準備」は不要。分からないことは聞けばOK
はじめて依頼するときにありがちなのが、「ちゃんと依頼できるか不安だから、まだお願いできない…」という“準備しすぎ”の状態です。
でも本来、オンライン秘書は「依頼の整理」そのものを一緒にやってくれる存在です。
- 文章がうまくまとまらない
- どんなフォーマットが必要か分からない
- 頭の中にあるイメージしかない
──そんな状況から一緒に伴走してくれるのが、いい秘書さんです。
✔「この作業、どう依頼すればいいですか?」という相談そのものが、最初の依頼になってもOKなのです。
5. よくある失敗とその乗り越え方
オンライン秘書を初めて利用する際に起こりがちな“失敗”は、実は技術的な問題ではありません。
多くの場合、コミュニケーションの“すれ違い”や“前提のズレ”が原因です。
ここでは、実際によくある失敗パターンをいくつか取り上げ、その背景と解決策をわかりやすくご紹介します。
過去に作成したコラムもご参照ください。
初めてのオンライン秘書依頼で失敗しない3つのコツ【依頼文テンプレ付き】
https://choco-hisho.nfa-g.com/2025/04/22/column_12-3/
失敗①:依頼内容がざっくりすぎた(伝わらなかった)
💬 よくあるケース
「こんな感じで仕上げてほしい」
「とりあえずまとめておいて」
「資料を整えてほしい」
──このようなあいまいな依頼文で伝えた結果、「なんだか思っていたものと違う…」という納品物が返ってくる。
🔧 どう乗り越える?
- 「誰のために」「何に使う資料か」「どんな状態なら完成か」を明示する
- 過去に似たようなアウトプットがあれば共有する
- 最初は“完成形”ではなく“たたき台”で方向性を確認してから仕上げてもらう
例えば:「社内会議で使うから、過去3年の数字をグラフにして見やすく整えてください。参考に昨年の資料を添付します」
失敗②:返答や素材の提供が遅れて作業が止まってしまった
💬 よくあるケース
依頼後にオンライン秘書からの質問や確認が届いたものの、返信が遅れ、タスクが止まってしまう。
→「進んでない」「予定より遅れてる」と感じてしまう。
🔧 どう乗り越える?
- 稼働日と稼働時間を把握し、「この時間までに素材を渡す」など逆算して準備
- “確認が必要な項目”を一覧化しておく
- Slackなどのチャットツールで「即答できない項目/あとで確認する項目」を分ける工夫
補足:「こちらの資料は月曜午前中にお送りします」など、やりとりに“期限”を加えるだけでもスムーズに。
失敗③:依頼できる範囲を誤解していた
💬 よくあるケース
「秘書って、もうちょっと何でもやってくれると思ってた」
「もっと提案してくれると思ってた」
──思ったよりできることが少ない、という誤解による落胆。
🔧 どう乗り越える?
- 依頼前に「できること/できないこと」をざっくり確認しておく
- 相談ベースで「これはお願いできる?」と投げかける
- 得意分野が合っていなければ、担当を変えてもらう選択肢もあり
「ちょこっと秘書」などのサービスでは、得意ジャンル(SNS系、経理系、資料作成系など)に応じて適任者のマッチングが可能です。
失敗④:「もう少し早く伝えておけばよかった…」という後悔
💬 よくあるケース
「今日中にやってもらいたい作業を、当日午前に依頼」→その時間には稼働しておらず依頼できなかった。
🔧 どう乗り越える?
- オンライン秘書の“稼働時間”をあらかじめ確認し、前日までの依頼を心がける
- タスクが生まれた時点で「後日依頼予定タスク」としてメモしておく(NotionやGoogle Keepなど)
補足:急ぎの作業が多い場合は、「急ぎの作業が発生しやすい時間帯に稼働出来る」秘書を最初から希望すると◎
失敗⑤:「なんとなく頼みづらくて、うまく活用できなかった」
💬 よくあるケース
「忙しそうに見える」「こんなこと頼んでいいのかな…?」と思って遠慮してしまい、使いこなせないまま時間だけ過ぎてしまう。
🔧 どう乗り越える?
- “使ってもらうこと”がサービスの本質。遠慮なくお願いするほうが双方にとって良い関係に
- タスクを小分けにして「試しにこの1件から」で気軽に依頼
- 「○○が苦手なので、できれば補ってほしい」と正直に伝えると◎
まとめ:最初の1歩がすべてを変える
「ちょっと手が足りない」
「この作業、誰かにお願いできたらな」
「でも人を雇うのは難しいし、外注なんてハードルが高そう…」
そう思っている方にこそ、オンライン秘書は選択肢になり得ます。
本記事では、「オンライン秘書って何?」「初めて使うときは何をどうすれば?」という不安に寄り添いながら、依頼のコツ・おすすめ業務・実際の事例をご紹介してきました。
最初からすべてを丸投げする必要はありません。
最初から完璧な依頼ができなくても構いません。
大切なのは、「まずは1つ、頼んでみる」という一歩です。
たとえば──
- 広告のバナー画像の作成
- 日程調整のやり取り、Googleカレンダーの入力とリマインドをお願いしてみる
- 請求書を作成してもらう
- Instagram投稿の予約を依頼してみる
それだけでも、ふだんの業務の中に「自分以外が動いてくれる」という感覚が加わり、視界がぐっと開けてくるはずです。
そして、この“一度頼ってみた経験”こそが、業務の整理、チームの成長、働き方の見直しなど、次の変化への大きなきっかけになります。
✔ この記事のポイントを振り返ると…
- オンライン秘書はあなたや会社に寄り添う相棒。必要なときに、必要な分だけ頼れる存在です
- 依頼のコツは「目的よりも困っていることを伝える」こと
- 初めての依頼には、SNS更新・資料整形・リサーチ・日程調整のやりとりなどがおすすめ
- 「ちょこっと」から始めることで、失敗のリスクを最小限に抑えられます
- じっくり採用・引継ぎを進める“つなぎ役”としての活用も有効です
【PR】ちょこっと秘書なら、あなたの「最初の一歩」を全力サポート
「オンライン秘書を使ってみたいけれど、本当に任せられるか不安」
そんな声にお応えするために、ちょこっと秘書では“初めてのご依頼”を丁寧にサポートしています。
- 月10時間〜から契約OK
- 必要な曜日・時間だけ、必要な業務だけの利用も可能
- 「どう頼めばいいか分からない」という段階から伴走
- 実績豊富なスタッフが、ヒアリングから納品までしっかり対応
資料整備・業務の整理・マニュアル作成なども含め、最初の一歩から「任せてよかった」と思える体験をお届けします。
🔗 詳しくはこちら: https://choco-hisho.nfa-g.com/
あなたの働き方はきっと変わります。
ちょこっと秘書は、その最初の一歩を支えるパートナーです。
著者 プロフィール

株式会社エヌエフエー
事業部 戦略室 主任
林 正幸
1995年生まれ、入社5年目。それまでは倉庫現場の派遣スタッフとして従事。
ゲームクリエイター、倉庫内派遣スタッフ、そして株式会社エヌエフエーに至る。
音楽が大好きでHIPHOPからオーケストラまで幅広い。最近のオススメは「ずっと真夜中でいいのに」。
興味のある物は飛び付いてとにかく満足するまでやる、調べる、楽しむがモットー。